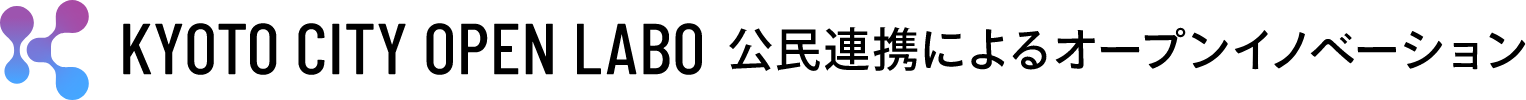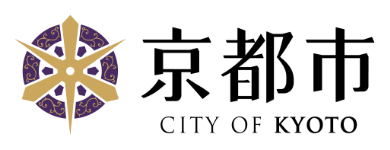Story

高齢者福祉の現場とペット
高齢者福祉における課題は多岐に渡りますが、そのうちのひとつに、飼い主が高齢で、ペットの面倒を見られなくなるという事態があります。高齢者福祉の現場であるヘルパーやケアマネージャーのなかには、放っておけないという気持ちから、本来業務の責任を超えて、取り残されたペットの面倒を見たり、代わりの飼い主を探したりする人もいるそうです。
動物愛護センターの2010年からの調査でも、犬及び猫についての引き取り理由が「飼い主の体調不良・死亡」である割合が、常に30%~50%程度を維持し続けており、今後、増えることがあっても減ることはないだろうという予測があります。
高齢者とペットの問題は、待ったなしの状況にあります。
高齢者の生活の質(QOL)を高めてくれる「ペット」という存在
仕事や学校などで日中不在がちな若い世代と違い、一般的に高齢者は在宅の時間が長い傾向があります。ともすれば生活の質(QOL)を下げてしまうこの傾向は、ペットを飼う際にはメリットになります。飼い主がペットと長時間一緒に過ごすことができる環境は、ペットにとっては安心ができる材料になりますし、飼い主である高齢者自身も、孤独感を癒し、生活リズムを整え、うるおいのある生活を送ることができるようになります。
このように高齢者のペット飼育は本来相性が良いと言えるものですが、自分の年齢を考えて、あらたにペットを飼うことをためらう高齢者も少なくありません。衝動的にペットを飼い始める無責任な飼い主が問題になる中で、ペットの将来を真剣に考え、諦めている高齢者のみなさんにこそ、ペットと幸せになって欲しいと考えています。高齢だから、という理由でペットを飼ってはいけない、そんな社会にはしたくないのです。そのためにはペットのことを真剣に考えてくださる方々が、安心してペットを飼うことができる環境を作っていく必要があります。
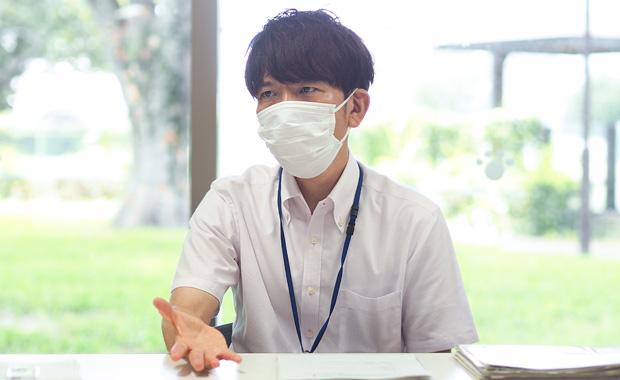
高齢者が安心してペットを飼育するために求められる環境
高齢者が安心してペットと過ごすことができるように、すでに市民団体や企業のさまざまな取り組みがあります。高齢者が一人で飼うことが困難になったとき、散歩補助等、飼育を支援してくれるサービス。飼い主の死後、ペットを引き取って最期まで飼ってくれたり、代わりの飼い主を探してくれるサービス。多くの場合、あらたにペットを飼うときには、ペットが子供の状態から始めますが、高齢者向けに、高齢のペットとのマッチングをしているところもあります。動物愛護センターでも、ペットのための終活セミナーといった高齢者向けのイベント開催などを行っています。
こういった取り組みがより周知され、利用しやすくなることで、安心してペットとの生活を選択することができます。

多様なソリューションを求めます
今回のオープンラボでは、高齢者福祉の最前線である地域包括支援センターに寄せられているペットに関する課題を解決できる方々を求めます。高齢者とペットに関する問題は、現在進行形で動いています。動物愛護センターと地域包括支援センターの協力関係を使って、いままで地域包括支援センター単体では解決できなかったペットの問題を、オープンラボ参加民間団体の皆さんと一緒に解決してゆくことを目指します。
「高齢者とペット」についての多様なソリューションを持つ方々の参加を歓迎します。飼い主の飼育支援、新たな飼い主とのマッチング、飼育についての啓発等、さまざまな分野の知見をお寄せください。まずは支援のありようにも多くの形があるということを知っていただくことが必要です。高齢でも安心してペットと生活できる仕組みづくりのために、みなさんのご参加をお待ちしております。