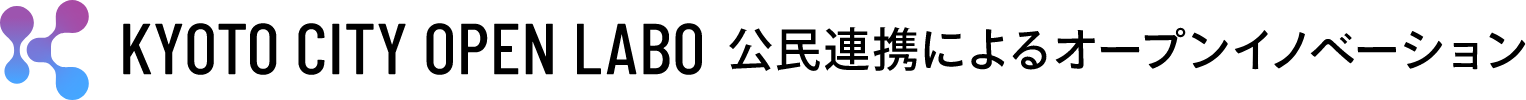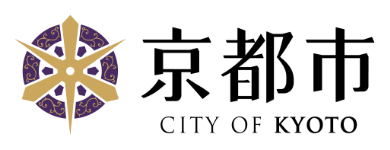Story

放置竹林という問題
「京都の竹林」といえば、嵐山の竹林の小径を思い浮かべる方も多いことでしょう。明るく青々とした竹林のなかにある、竹垣に挟まれた小道は、四季を通して、さまざまな表情を見せてくれます。しかし、実際には京都でも、そのような美しい竹林はほんの一握りでしかありません。その多くが荒れ果てた「放置竹林」として、むしろ京都の景観を損ねてしまっているのが現状です。
京都市内には約660haの竹林が存在しています。かつては美味しいたけのこや竹材を生み出す場として手入れされていたそれらの竹林も、今では農家のリタイアや竹材の需要減から、全体の4割が人の手の入っていない放置竹林になっていると言われています。
竹はたいへん成長が早い植物で、孟宗竹では数箇月で高さ20メートルに達します。ほんの2~3年放置しただけで、竹林は真っ暗でうっそうとした状態になり、10年もすると人が立ち入ることすら難しくなります。また、地下茎でどんどん領域を拡げるため、他の植物の成長を阻害し、周辺の宅地や道路等にも侵食していってしまいます。そうして手のつけられなくなってしまった竹林を元の状態に戻すのは、たいへん困難です。
健全な竹林を維持管理するためには、所有者が整備を行うことが望ましいのですが、収益にならない竹林に手間をかけることには難しさがあります。竹林の伐採や整備のための行政の助成金等もありますが、「最長3年まで」など年限があるものが多く、それだけで続けていけるわけではありません。継続的な竹林の整備のために、継続的な竹林からの収益が求められているのです。
NPOによる放置竹林対策
市内でもとりわけ竹林の多い西京区大原野地域では、NPOによる取組が進められています。地域の竹林のほとんどが私有地であり、京都市のような行政が介入しづらいのが実情である中、2009年に発足した「NPO法人 京都発・竹・流域環境ネット」は、地域に密着し、竹林の所有者と関係を構築することで、放置竹林の問題の解決を図っています。
NPOでは、新たなたけのこ農家を育成したり、竹材を使う企業と竹林の所有者を繋げることで、放置竹林を減らしてきました。継続的に農家の手が入り、企業が関わることで、竹林の管理も行われることになります。活動の成果から10haほどの竹林の改善が行われましたが、解決までの道のりはまだまだ遠いと言わざるを得ません。

竹の有効利用の難しさ
放置竹林は、京都だけでなく全国的な問題ですが、放置竹林を抜本的に解決するような画期的なアイデアはまだ出ていません。竹は成長が早い反面、内部が空洞なので、利用できる部分が一般にイメージされているよりあまりありません。また、大規模な需要が未発達の現状では、コストメリットもあまり見出せません。竹林の所有者のほとんどが個人であることも、ビジネスの分野にとっては参入障壁になっています。
「竹ビジネス」の難しさは、素材そのものの難しさもありますが、製造、加工、販売のいずれの分野においても、竹についての情報や体制が不足していることが理由として考えられます。竹材の性質や「京都の竹」の優位性など、調査の道もまだ半ばです。
大量消費かブランディングか。竹林資源の活用の道を探るために
今回のオープンラボでは、できるだけたくさんの竹を有効利用できる方法を広く求めます。また、竹素材の商品開発や、竹林の空間利用等のアイデアに加えて、「竹ビジネス」の難しさを解消してくれるような、ブランディングや販路の確保などの仕組みづくりも歓迎します。京都市の竹林の保全と景観維持のため、皆様のお知恵をお貸しください。