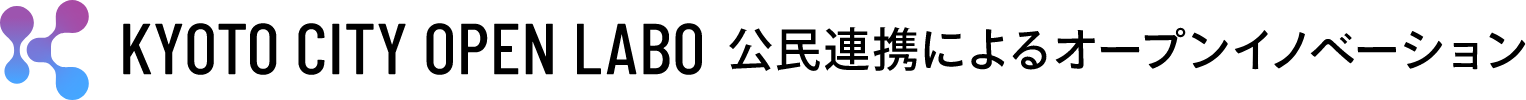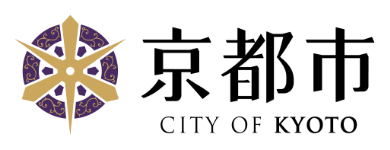新たな賑わいを創り出す、kokoka京都市国際交流会館の前庭広場の利活用
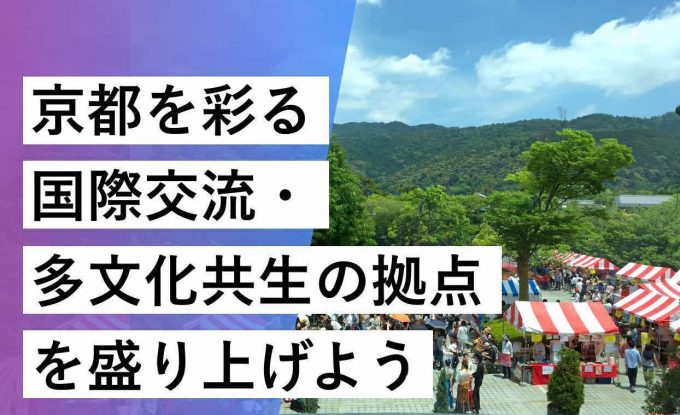
課題のポイント
実現したい未来
・市民の国際交流の拠点として、日々、外国籍市民を含む多くの市民が集い、気軽に日本語や日本文化に触れられる場や、異なる文化への理解を深めるきっかけや情報に出会う場がある。
・市民、事業者、民間団体などが積極的に施設を利用し、イベントホールや会議室を通じて、多様な国や地域の人々が出会い、つながっていける。
・互いの文化を尊重し合い、自然に理解を深め合える、そんな国際交流と多文化共生の象徴となる施設を目指したい。
現状
・kokoka京都市国際交流会館は、鉄骨鉄筋コンクリート造3階建の本館と和風別館から成り、交流ロビーには情報サービスコーナーやキッズスペース、カフェがあり、2階のkokoPlaza(図書・資料室)、多目的ルーム(授乳やお祈り等)も自由に利用できる。イベントホールや大小様々な貸会議室もある。
・また、「京都市外国籍市民総合相談窓口」を開設し、多言語で相談に応じている。国内外の人々が互いの文化を理解し、共に暮らせる社会の実現を目指して、留学生支援、ボランティア活動等、京都の国際化の拠点として運営し、年間延べ24万人(令和6年度)が来場する。
・前庭広場の貸し出しも行っているが、指定管理者、企業や団体による単発のイベント利用(食を通じたイベント)にとどまり、そのポテンシャルを活かしきれていない現状にある。
・多文化共生を願い市内で活動する事業者との連携は十分とは言えない。
解決したい課題
京都市の「多文化共生社会」の実現を目指す事業者、団体との連携促進
① 来場者への情報提供や連携イベントの他、様々な連携の可能性を模索したい
②「前庭広場」の実験活用により、新たなにぎわいを創出したい
想定する解決策
○kokoka京都市国際交流会館の前庭スペースを活用した、多文化交流をはじめとする様々な活性化のアイデアを募集します!
・日本人も外国人も気軽に集える空間づくり
(例)多文化交流ワークショップの開催のほか、踊りや大道芸、アート作品などを気軽に発表できる場としての活用による、外国文化などを知る機会の創出や子どもから大人まで楽しめるイベントの開催 など
・近隣エリアの地域資源との連携による魅力ある取組の創出
(例)琵琶湖疏水、蹴上インクライン、京都市動物園 など
・前庭広場の利用促進にむけたPR強化
・様々な視点で(継続的に)企画・実施できる市民団体等に前庭広場等の利用を促すためのコーディネート機能の強化
※フード系イベントは本提案の対象外とします。フード系イベントで前庭広場の活用を希望される場合は、直接京都市国際交流協会までご連絡ください。
民間組織側の想定メリット
・施設は春秋の観光シーズンを中心に人の往来が多い地域にあり、多くの人々の目にとまるため、広く取組の周知が期待できる。
・本市ホームページや、指定管理者((公財)京都市国際交流協会)が有する広報チャンネル(協会メルマガ)への掲載を通じたPRが可能(無料で協力可能)
.jpg)

募集概要
| 担当課 | 京都市総合企画局国際都市共創推進室国際担当 |
|---|---|
| 担当部署の事業の概要 | 多文化共生施策の推進、姉妹都市等との交流、世界歴史都市会議・世界歴史都市連盟・国際交流会館等に関する事務 |
| 背景 | ・kokoka京都市国際交流会館は、1978年に京都市が発表した「世界文化自由都市宣言」に基づき、市民の国際交流の拠点として1989(平成元)年にオープン(平成18年から指定管理制度を導入し、現在、(公財)京都市国際交流協会により運営)。 |
| 実現したい未来 | ・市民の国際交流の拠点として、日々、外国籍市民を含む多くの市民が集い、気軽に日本語や日本文化に触れられる場や、異なる文化への理解を深めるきっかけや情報に出会う場がある。 |
| 現状 | ・kokoka京都市国際交流会館は、鉄骨鉄筋コンクリート造3階建の本館と和風別館から成り、交流ロビーには情報サービスコーナーやキッズスペース、カフェがあり、2階のkokoPlaza(図書・資料室)、多目的ルーム(授乳やお祈り等)も自由に利用できる。イベントホールや大小様々な貸会議室もある。 |
| 検討経緯・これまでに実施したことがある施策等 | ○「京都市外国籍市民総合相談窓口」を開設し、多言語で相談や留学生支援を実施 |
| 解決したい課題 | 京都市の「多文化共生社会」の実現を目指す事業者、団体との連携促進 |
| 想定する解決策 | ○kokoka京都市国際交流会館の前庭スペースを活用した、多文化交流をはじめとする様々な活性化のアイデアを募集します! |
| 民間組織側の想定メリット | ・施設は春秋の観光シーズンを中心に人の往来が多い地域にあり、多くの人々の目にとまるため、広く取組の周知が期待できる。 |
| 提案企業に求める専門性 | – |
| 提供可能なデータ・環境等 | – |
| スケジュール感・主要なマイルストン | 随時募集 |
| 事業実施にあたっての留意点、制約等 | 【「前庭広場」の貸出について】 |
| 参考情報 | ・kokoka京都市国際交流会館HP |
| 今後の展開想定 | 前庭広場の活用などを契機として、様々な企業や団体との連携の可能性を模索していきます。 |
| 提案の提出期限 | 2025年11月20日〜2026年3月31日 |
| 目指すSDGsのゴール | |