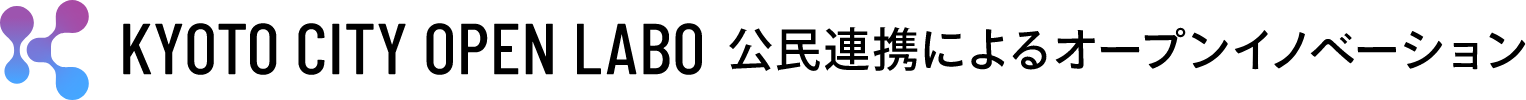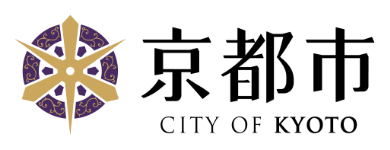この課題の募集は終了しました
フードテック等を活用した食品ロスの削減につながる取組の創出

課題のポイント
実現したい未来
市内食品関連事業者がフードテックサービスを含むあらゆる手法を活用することにより、事業系食品ロスがこれまで以上に削減されている状態
現状
〇京都市の食品ロスについて
・京都市の「食品ロス(手付かず食品+食べ残し)」は、家庭系と事業系を合わせて年間5.0万トン(令和5年度)発生しており、ごみ量の約13%(ごみ量の約4割が生ごみ、生ごみの約4割が食品ロス)を占める。
・本市では、食品ロス削減目標を全国で初めて設定し、取組を進めてきた結果、食品ロスは減少傾向で推移し、ピーク時から4割以上の減量が進んでいる。
・しかしながら、令和12年度4.6万トンの目標に向けては、特に事業系の食品ロスについて、より一層の削減が必要である。
〇フードテックサービスについて
・フードシェアリングアプリや食品の需要予測といったフードテックサービスは、食品ロス削減などの社会課題の解決が期待されているが、比較的新しいサービスであり、まだ十分に世間に普及していない現状もある。
・食品関連事業者においては、フードテックサービスの導入に必要な費用に対して、得られる効果やメリット(ごみ削減だけでなく、店舗のイメージアップや新規顧客獲得など)が十分に理解されていない、あるいは、中小事業者の場合、新たな取組を検討、開始するための人員やコストの課題感もあると考えられる。
※フードテック…デジタル技術等で食分野における課題を解決し、食の可能性を広げていく技術やビジネスモデル
解決したい課題
市内食品関連事業者において、食品ロス削減につながるフードテックサービスの認知・利用を拡大させ、事業系食品ロスの削減及び市民の行動変容につなげたい。
想定する解決策
市内食品関連事業者に、食品ロス削減につながるフードテックサービスの認知を拡大し、取組を後押しするための提案
(例)
・食品関連事業者に対するサービス導入の支援(イニシャルコストの支援など)
・サービスの利用拡大に向けた京都らしい手法の提案(具体的な手法、京都の食文化、学生のまちなどの特色を活かしたアプローチなど)
・フードテックサービスを活用した、これまでにない新たな取組の実証実験
・食品関連事業者に響くような分かりやすい情報発信の手法
→上記は一例であり、食品ロスを削減するためのフードテックに関するご提案を広く募集します!
民間組織側の想定メリット
・本市との連携による自社サービスの広報促進
→本市の広報チャネルも活用し、市内食品関連事業者への積極的・効果的なPRを実施可能(市HP「食品ロスゼロプロジェクト」内「食品ロスを減らそう!お結び広場」ページへの情報掲載など)
・サービス利用事業者の増加による収益増加
・京都の食品関連事業者等との関係構築が可能
・他都市でも同様の課題を抱えている自治体は多く、事業の横展開も期待可能
(モザイク)2.jpg)
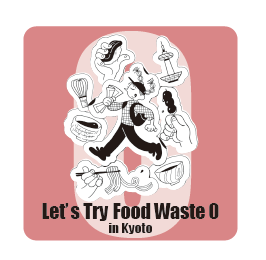
募集概要
| 担当課 | 京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課 |
|---|---|
| 担当部署の事業の概要 | ごみの減量に向けた企画や意識啓発。一般廃棄物を生じる事業者等に対する指導等 |
| 背景 | 食品ロスの削減につながる市民及び事業者の取組促進 |
| 実現したい未来 | 市内食品関連事業者がフードテックサービスを含むあらゆる手法を活用することにより、事業系食品ロスがこれまで以上に削減されている状態 |
| 現状 | 〇京都市の食品ロスについて 〇フードテックサービスについて |
| 検討経緯・これまでに実施したことがある施策等 | ・令和3年度には、AI や IoT 等を活用した食品ロス削減に効果的なサービスについて、食品関連事業者向け説明会を開催したが、コロナ禍の影響もあり、食品関連事業者の参加やその後の展開は限定的であった。 |
| 解決したい課題 | 市内食品関連事業者において、食品ロス削減につながるフードテックサービスの認知・利用を拡大させ、事業系食品ロスの削減及び市民の行動変容につなげたい。 |
| 想定する解決策 | 市内食品関連事業者に、食品ロス削減につながるフードテックサービスの認知を拡大し、取組を後押しするための提案 |
| 民間組織側の想定メリット | ・本市との連携による自社サービスの広報促進 |
| 提案企業に求める専門性 | – |
| 提供可能なデータ・環境等 | ターゲットとなる食品関連事業者(「京都市食べ残しゼロ推進店舗」(約1,700店舗など)への周知広報、市民に対する周知広報は、本市が予算の範囲内で実施する。 |
| スケジュール感・主要なマイルストン | 令和7年6月~12月頃の事業実施、令和8年1月以降の事業効果の発信を希望。食品ロス削減月間である10月も意識してスケジュールを相談したい。 |
| 事業実施にあたっての留意点、制約等 | ・事業効果(食品ロス削減効果)を発信したいため、効果測定が可能な仕組みが望ましい。 |
| 参考情報 | ・食品ロスゼロプロジェクト |
| 今後の展開想定 | 得られた成果を踏まえて、次年度以降の連携や更なる取組の促進も検討していきたい。 |
| 提案の提出期限 | 2025年4月23日〜10月31日 |
| 目指すSDGsのゴール | |
この課題の募集は終了しました
成立案件の一覧へ戻る