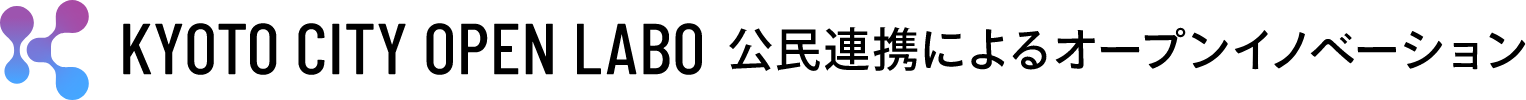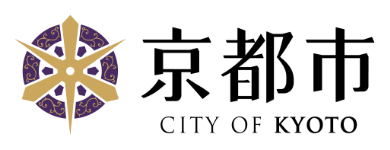Story

持続可能な社会と消費生活
消費行動を通じてより良い社会を目指す考え方として、近年注目を集めているのが、「エシカル(倫理的)消費」です。これは、消費者が地球温暖化などの社会課題について考え、課題に取り組む事業者を応援しながら人・社会・地域・環境に配慮した消費行動を行うことで、より多くの人が持続可能な生活を送れるようになり、地域の活性化や世界の未来を変えていくことを目指すものです。
「エシカル消費」の考え方に基づき消費行動を変容していくことは、京都市が力を入れて取り組んでいる脱炭素社会の構築やSGDsの実現にとっても重要です。これまで京都市では、「エシカル消費」の啓発活動として、親子を対象としたワークショップイベントの開催や、市民も参加できる大学での消費者教育講座を行ってきました。また、市内の小売店と協力してショートムービーを作成したり、イメージキャラクターを用いた情報発信に取り組んでいます。
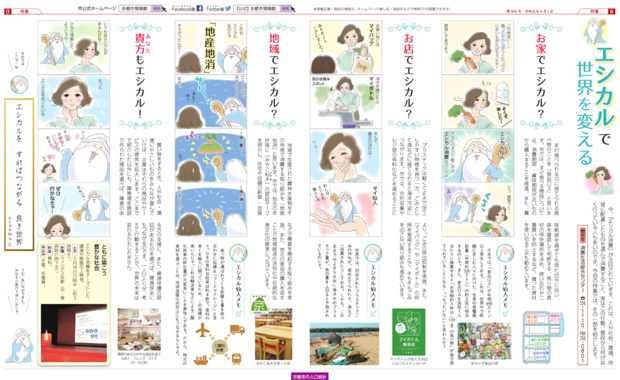
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000708.html
わかりづらい「エシカル」
「エシカル消費」は、持続可能な社会を構築する上で欠かすことのできない概念ですが、一方で、わかりづらいという問題を抱えています。2020年の消費者庁による全国を対象とした消費者意識調査※では、環境を表す「エコ」という言葉の認知度が72%だったのに対して、「倫理的消費(エシカル消費)」の認知度はわずか12%でした。
「エシカル」という英語がそもそも難しいことに加えて、フェアトレード、地産地消、環境配慮、伝統産業等々、カバーする範囲の多様さも、概念を理解する上でのハードルを高くしているようです。また、値段の安い商品とエシカルで値段の高い商品を並べたときに、高いものを選択することの難しさもあり、なかなか広がりにくいのではないかと考えられます。
- ※ エシカル消費に関する消費者意識調査 | 消費者庁
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/ethical/investigation/
小売事業者による取り組みの重要性
「エシカル消費」の広がりにくさに向き合ううち、私たちは小売事業者による取組の重要性に着目するようになりました。エシカル消費に消費者が「自分ごと」として取り組むためには、まずは日常的な消費行動の場であるスーパーなどの小売店舗が、エシカル消費を実践しやすい場となっていることが不可欠だと考えたのです。
エシカル消費の概念を導入することで、商品の仕入れ方法や陳列方法に変化が生まれれば、消費者の消費行動にプラスの効果が生まれることが期待できます。また、エシカル消費を意識した仕入れや商品管理を行うことは、短期的には店舗における廃棄物の削減や売上げの変化に、長期的には良好な経済的循環につながることが期待できます。持続可能な消費のモデルに取り組むことは、潜在的な消費者のニーズに向き合うことです。これからの持続可能な社会に向けては、消費者だけではなく事業者の意識が変わっていくことが重要なのです。
小売店向け社内研修プログラムの作成と実施
この実証実験では、「エシカル消費」に関する小売店向けの社内研修プログラムを作成、実施したいと考えています。想定する対象は小売店の事業者ですが、NPOなどの参加も歓迎します。社内研修プログラムの作成と実施にあたっては、京都市では必要に応じて、資料の提供や講師の派遣などを行うことができます。

京都に息づく価値観と「エシカル消費」
「エシカル消費」の考え方は、大量生産・大量消費の経済活動を見直す役割として欧米で生まれ、近年になって日本でも取り組まれるようになったもの。そう考えると、定着させるのが難しい考え方のようにも見えます。しかし、もともと日本には「目利き」「物を長く大切に使う」「必要な分だけ使う」「季節感を大切にする」といった価値観があり、京都に暮らす人々は古くからそれらを自然に実践してきていました。「エシカル消費」は、決して私たちの生活に馴染まないものではありません。
このプログラムは一回のみのプログラムであってはならないと考えています。そのため、研修の効果測定の指標について検討したり、より良い研修プログラムの模索を継続的に続けていただける事業者であることを求めます。「エシカル消費」という概念を採り入れ、文化として継続的に取り組んでいただける、「使い捨て」ではない有為な研修プログラムを、事業者の皆さんと共に構築できたらと考えております。